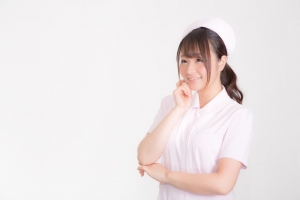出生前診断を受けるべき年齢は?高齢出産ほど先天性疾患に格段になりやすい件。
Canteenです。
30代以降の方の出産も珍しくない時代ですが、出産の年齢が高くなればなるほど、ダウン症などの先天性疾患のリスクが高くなります。
先天性疾患の有無を妊娠中に知ることができる方法に出生前診断がありますが、検査方法によっては流産のリスクがありますし、健康保険の給付がないため検査費用は全額自己負担です。
そうした出生前診断の流産リスクや費用負担を踏まえて、ここからは、
- そもそも先天性疾患とは何なのか
- 先天性疾患の年齢別発症確率
を確認しながら、出生前診断を受けるべきかどうかや受けるべき年齢について考えていきます。

先天性疾患とは?
例えば、ダウン症は最も一般的な先天性疾患です。その原因は染色体異常が原因です。染色体というのは、遺伝情報の書き込まれたDNAの集まりです。2本の染色体で1対になっています。人間には23対(46本)の染色体があります。しかしダウン症の場合、21番目の染色体に異常があり通常2本の染色体が3本ある状態になっています。
このような染色体異常や遺伝子異常が原因の先天性疾患の場合、出生前診断を行えば胎児に先天性疾患があるかどうかを調べることができます。
ここからは、それぞれの先天性疾患の症状についてご紹介していきます。
また、先天性疾患のあらましについてはNIPTコンソーシアムのホームページにわかりやすくまとまっていますので、ご紹介しておきます。
21トリソミー(ダウン症)
MSDマニュアル(ダウン症候群)に詳しくまとまっていますので、ご紹介しておきます。
簡単にまとめますと、
- 21番目の染色体が通常2本のところが3本ある。
- 最も頻度の高い先天性疾患である。
- ダウン症候群の小児の大半は、死亡することなく成人になる。
- 合併症として知的障害、難聴などがある。
MSDマニュアルにもあるとおり、知的障害の程度には幅があります。
18トリソミー(エドワーズ症候群)
MSDマニュアル(18トリソミー)に詳しくまとまっていますので、ご紹介しておきます。
簡単にまとめますと、
- 18番目の染色体が通常2本のところが3本ある。
- 出生6000人当たり1例の頻度で発生するが,自然流産となることが多い。
- 患児の半数以上は生後1週間以内に死亡し,生後1年まで生存する割合は10%未満である。
- 生存した場合も著明な発達遅滞と機能障害がみられる。
自然流産も多く、産後も死亡確率が高い先天性疾患です。
13トリソミー(パトウ症候群)
MSDマニュアル(13トリソミー)に詳しくまとまっていますので、ご紹介しておきます。
簡単にまとめますと、
- 13番目の染色体が通常2本のところが3本ある。
- 出生約10,000人当たり1例の頻度で発生する。
- 患児の大半(80%)は病状が重いために生後1カ月を前に死亡し,1年以上生存できる割合は10%未満である。
- 乳児期早期には無呼吸発作が頻繁に発生する。知的障害は重度である。
18トリソミーと同様に、産後も死亡確率が高い先天性疾患です。
その他の先天性疾患
wikipediaを見ていただくとわかりますが、その他にもたくさんの種類の先天性疾患があります。
中でも、上記の21,18,13トリソミーに次いで多い先天性疾患は『性染色体異常』です。MSDマニュアル(性染色体異常)をご覧いただくと分かりますが、
- ターナー症候群(出生女児の約1/4000に発生するが、99%が自然流産)
- クラインフェルター症候群(出生男児の約1/700に発生)
- 47,XYY症候群(出生男児の約1/1000に発生)
が紹介されています。これらの発症確率は割と高いですね。
年齢別の先天性疾患の発症確率
先天性疾患の発症確率は高齢出産になればなるほど格段に上がります。ダウン症の場合、20歳では1/1441の確率ですが、40歳ではなんと1/84の確率まで跳ね上がります。下表をご覧ください。18トリソミー、13トリソミーも確率がめちゃんこ跳ね上がっています。
|
母体年齢
(出産時) |
ダウン
症候群 |
18トリソミー
|
13トリソミー
|
|
20
|
1/1441
|
1/10000
|
1/14300
|
|
25
|
1/1383
|
1/8300
|
1/12500
|
|
30
|
1/959
|
1/7200
|
1/11100
|
|
35
|
1/338
|
1/3600
|
1/5300
|
|
36
|
1/259
|
1/2700
|
1/4000
|
|
37
|
1/201
|
1/2000
|
1/3100
|
|
38
|
1/162
|
1/1500
|
1/2400
|
|
39
|
1/113
|
1/1000
|
1/1800
|
|
40
|
1/84
|
1/740
|
1/1400
|
|
41
|
1/69
|
1/530
|
1/1200
|
|
42
|
1/52
|
1/400
|
1/970
|
|
43
|
1/37
|
1/310
|
1/840
|
|
44
|
1/38
|
1/250
|
1/750
|
|
45
|
1/30
|
─
|
─
|
引用:Gardner RJM. Chromosome Abnormalities and Genetic Counseling 4th Edition, New York, Oxford University Press 2011
こんな感じで発症確率が上がりますので、高齢出産の方にとっては出生前診断が重要になってきます。40歳になるとダウン症についてはなんと1/84の確率です。
何歳から出生前診断を受けるべきなのか
最も頻度の高いダウン症を例に見てみると、30〜35歳にかけて発症確率がぐんと上がっています。そのため、出生前診断を受けるべき年齢の1つの目安として30〜35歳というのが考えられるかなと思います。
また、出生前診断の中でも陰性的中率(陰性と判断された中で実際に陰性である確率)の高い新型出生前診断(NIPT)は、原則35歳以上でないと受けられないことになっていることから、35歳以上は先天性疾患のリスクが高いと日本では考えられているのかもしれません。
まとめ
先天性疾患の確率は20代であればかなり低いですが、30歳を超えてくるとぐぐっと上がってきます。色々な考え方があるかとは思いますが、もし先天性疾患の不安が大きいのであれば、出生前診断を受けるという選択肢もあるかと思います。
ただ、出生前診断は万能ではありません。
出生前診断で全ての先天性疾患の有無を検知できるわけではないです。さらに、仮に陽性だとしても、例えばダウン症の場合、NIPTでの30歳の陽性的中率(検査結果が陽性で実際に陽性である確率)はわずか61%です。つまりNIPTで陽性と判断された場合、約40%は偽陽性です。そのため、NIPTの検査結果が陽性の場合、基本的には羊水検査や絨毛検査による確定診断を受ける必要が出てきます。(陰性的中率は年齢によらず99%です。)
より詳しくはこちらの記事をご覧ください。
ただ、羊水検査や絨毛検査には流産のリスクがあります。流産のリスクを負ってまで確定診断に望むことが大切かどうかも考える必要があります。
こちらの記事でどういう先天性疾患がどれくらいの確率で発症するのかをより具体的に認識いただけたのではないでしょうか。皆様が出生前診断をうけるかどうかを考えるための一助になれば幸いです。
また、悩ましい出生前診断ですが、悩んでいる時間はあまりありません。可能な限り早期に出生前診断が可能な病院を受診することをおすすめしてます。その理由は、こちらの記事をご覧ください。







 アメリカ・ニュージャージー州在住の会社員です。
アメリカ・ニュージャージー州在住の会社員です。